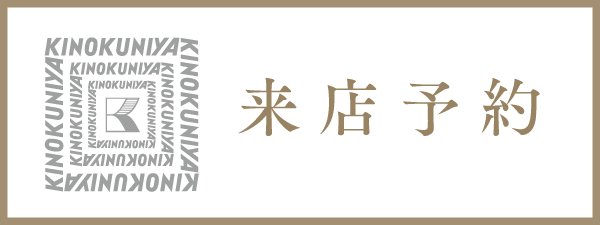このたび、調進所「紀ノ國屋 京町家」では、北山台杉を「盆栽」という新しい形でご紹介いたします。これは単なる販売ではなく、文化を守り、次代へとつなぐ試みです。
一鉢の盆栽に凝縮された台杉の景色は、しょうざんリゾートの庭園と同じく、観賞用台杉が持つ美と価値を身近に感じさせてくれます。その背後には、数百年を超えて受け継がれてきた林業技術と、数少ない職人の技があります。私たちが盆栽を取り扱う意義は、第一に文化の保護と継承、そして第二に現代の生活に伝統美を取り入れる提案です。鉢の中の台杉は、京都の自然と人の技の結晶であり、日常に静かな格調を添えてくれます。

北山台杉とは
京都・北山の山里で生まれた特異な杉、それが北山台杉(きたやまだいすぎ)です。通常の杉とは異なり、根元の台座部分から真っすぐ天に伸びる幹が数本立ち上がる姿は独特で、あたかも巨大な盆栽を思わせます。室町時代中期に考案された仕立て方は600年の歴史を持ち、北山杉の代名詞として知られています。一本の親木から複数の幹を更新させて使う林業技術は世界的にも稀有で、京都独自の知恵と文化を体現しています。
歴史と文化的価値
北山台杉から生み出される磨き丸太や垂木材は、茶室建築や京町家の床柱・天井材などに用いられ、長きにわたり京都の町並みと文化を支えてきました。その材は均整が取れ、光沢を帯びた木肌は日本建築の美を際立たせます。北山杉は「京都府の木」にも指定され、京都人の誇りとして今なお大切にされています。

鑑賞用台杉の誕生
本来は建材として利用されてきた台杉ですが、その美しい姿そのものに価値を見出し、観賞用として初めて庭園に導入したのが「しょうざんリゾート京都」です。昭和期、北山から樹齢350年以上の台杉を移植し、台杉は新たに「景観樹」「文化財的存在」としての命を得ました。
この試みは単なる造園ではなく、衰退の兆しを見せつつあった北山林業に光を当てる文化的貢献でもありました。しょうざんの庭園は、台杉の鑑賞的価値を国内外に知らしめる契機となり、その後の観賞用台杉の普及と保存に大きな役割を果たしたのです。
特殊な剪定技術と希少な職人
鑑賞用台杉は、建材生産とは異なる高度で特殊な剪定技術を必要とします。幹の高さや本数を揃え、庭園景観として均整のとれた美を引き出すには、長年の修練と卓越した感覚が不可欠です。この剪定技術を継承できる職人は、現在の日本でも数名に限られるほど希少とされ、その存在自体が文化財といえます。しょうざんリゾートが築いた観賞用台杉の庭園は、そうした職人たちの技と心を今に伝える場であり、その価値は極めて高いものです。
京町家と台杉
京町家に目を向ければ、床柱や垂木材に北山杉が使われていることに気づきます。町家の空間に凛とした趣を添えてきた背景には、北山台杉の存在がありました。台杉は建築材としての実用性と、観賞用としての美の双方を兼ね備える、京都ならではの「暮らしと文化を結ぶ木」なのです。